 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
消費税の事業区分の判定は、まず、第1種(卸売業)、第2種(小売業)、第3種(農・林漁業、製造業等)、第5種(不動産業、サービス業等)の順で、それぞれに該当する取引か否かを判定し、どれにも該当しない取引は第4種となります。
飲食店は、基本的に第4種ですが、行う取引によっては、第2種、第3種、第5種に該当する場合もあります。事業区分の判定は、取引ごとに行い、一の事業者で、一つのお店しか出していなくても、複数の事業区分の取引を行っている場合があります。 ・第2種に該当する取引の例 ⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等の缶ジュース、アイスクリームのテイクアウト(購入商品の性質・形状を変更せずに行う販売) ・第3種に該当する取引の例 ⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等のピザ、ハンバーガー等のテイクアウト(製造した商品の販売) ・第5種に該当する取引の例 ⇒コンパニオン派遣料、パーティ進行料、カラオケボックスやマンガ喫茶の施設利用料、割烹旅館における飲食代込みの宿泊料 複数の事業区分の取引を行っている場合、売上を区分経理する必要があります。区分経理していない場合は、すべての取引について、不利な事業区分が適用されます。 複雑な形態の飲食店は、一般課税(本則課税)の方が、むしろ、簡単な計算で済むこともあります。簡易課税=簡単な計算、とは必ずしも言い切れません。 PR |
 |
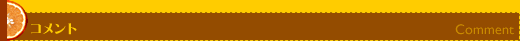 |
複雑な仕組み…
消費税というのは会社単位ではなく、事業単位でかなり細かいのですね。
ということは経理処理が複雑に… 簡易課税という名前も知らなかったのですが、=簡単と思っては穴に落ちてしまうところでした(汗)  わかばさん、コメントありがとうございます。
消費税の納税額の計算方法には、一般課税(本則課税)と簡易課税の2種類があって、好きな方を選べるのですが、税理士が関与していない個人事業者は、計算が簡単だという理由で、簡易課税を選択する人がけっこういらっしゃいます。 ほとんどの場合は、簡易課税=簡単な計算となるのですが、複数の種類にわたる商売をしている人は、一般課税も簡易課税も、どちらにしても計算が大変です。 税金って、払うのも大変ですが、払うための計算も大変です。
【2006/07/17 22:55】|
|
すみれ [ 編集する? ]
 |
 |
|
|
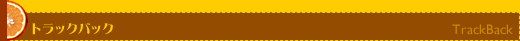 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |




