 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
赤字が続いている同族会社の中には、資金不足を社長からの借入れで賄っているケースがあります。社長にとって、会社への貸付金は相続財産を形成するので、社長が高齢で、かつ資産家であり、相続税が出そうな場合には、対策を打つ必要があります。
いわゆる社長借入金の実態は、社長の個人的な財産を売却して資金をつぎ込んだというような積極的な貸付のほか、社長に給料を払っていないにもかかわらず給与所得控除を有効に使うために役員報酬を計上し、支払えない分については社長借入金で処理するというような、過度な帳簿操作によって生じていることもあります。いずれにしても、そのままにしておくと、死亡した時に相続財産として扱われます。 相続への対策として、最も手っ取り早く行えることは、社長が会社に対して債権放棄をすることです。その場合、会社側では、債務免除益が発生し、法人税の課税所得にプラスされますので、当期が欠損であるか、繰越欠損がある場合に、その額の範囲内での債務免除にする必要があります。また、債務免除前後で会社の株価が変動する場合には、他の株主にみなし贈与課税が発生するので、財産状態を考慮して実行しなければなりません。 繰越欠損がない場合には、DES(デット・エクイティ・スワップ)という手法が有効です。DESとは、社長借入金を資本金に振り替える、つまり借入金の現物出資をすることです。ただし、状況によっては、DESも債権放棄と同様に、債務免除益や贈与税がかかることがあります。また、登記が必要であるとか、手続きも複雑になってきますので、DESは慎重に行わなければなりません。 債権放棄もDESもしないまま、不幸にして相続を迎えてしまった場合であっても、会社への貸付金が回収不可能又は著しく困難であると見込まれれば、相続財産に含まれません。原則として、相続財産の計算は相続発生時の現況で判断しますが、相続税の申告期限までに会社が清算され、現実に回収できなかった場合には、相続発生時において回収困難であったと認められているようです。相続発生後の会社の清算は、後継者がいない場合に有効な手段です。 PR |
 |
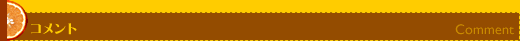 |
 |
|
|
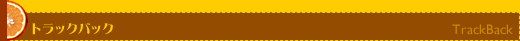 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |




